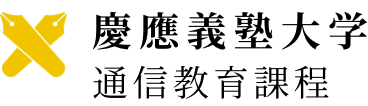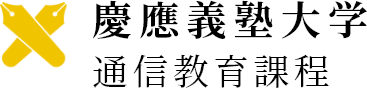会計の持つパワーと文化

商学部教授
深井 忠
読者の中には、会計は結局、計算手段に過ぎず、会計基準は退屈なルールの集合であると思われている方も多いのではなかろうか。確かにそうした面もあるが、本稿ではジェイコブ・ソール著、村井章子訳『帳簿の世界史』(文藝春秋、二〇一五)から二つのエピソードを取り上げ、会計学に少しでも興味を持っていただく契機を提供したい。
最初の舞台は東インド会社時代のオランダである。当時、オランダは貿易によって商業が極めて栄えていたが、それとともに会計が高度に発達し、多くの者が複式簿記を習得していたという。それは職業倫理の高さにもよるが、同国が海抜より低地にあり大洪水の被害を繰り返し受けていたことと関連している。乾いた土地を確保するためには堤防、排水システム、運河、水門等の管理が死活問題となる。その管理責任は自治組織である水管理委員会が担っていた。もしその資金が適切に運用されず、工事が適切に行われなければ、その地域は水没し、多数の者が命を落とすことになる。そうしたことが起きないように人々は正しい会計を求め、適切な監査を要求した。会計は多くの人命を支えていたわけである。
二つ目の舞台は大革命前夜のフランスである。ルイ一六世の治世下、財務長官ネッケルは、王家の財政を詳しく説明した﹁国王への会計報告﹂を公表した。それは前代未聞の出来事であった。これによって兵士への給与、宮廷・王室費に多額の支出が割かれ、社会福祉関係等の民生費はごく僅かであることが多くの国民の前にさらされた。しかし、それは既得権益を持つ貴族の反感を招き、国家機密の暴露と批判された。結局、ネッケルは罷免されるが、これがフランス革命の一因とされている。会計は人々の生命を左右するばかりか、時に大革命を引起こすパワーを秘めていたのである。
正しい会計を行うこと、それを適正に公表することは、現在では当たり前のように考えられているが、実はそれほど簡単なことではない。真実を述べることが反対勢力の抵抗に遭い、命の危険に晒されることも少なくない。それは政治的な力によって会計が歪曲され、真実が隠蔽されることを意味する。
だが、そうした社会が長続きしないことも歴史が繰り返し証明している。社会の繁栄は、正しい会計を行いそれに責任を持つことで初めてもたらされる。会計は単なる計算手段ではない。人々の生活に深く溶け込んだ文化である。さて、読者の皆さんはどうお考えであろうか。
『三色旗』2016年2月号掲載