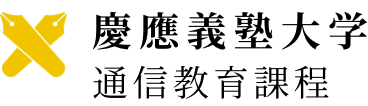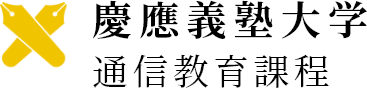ヴィヴァルディの「四季」

法学部教授
許 光俊
イタリアの作曲家、アントニオ・ヴィヴァルディ(一六七八―一七四一)のヴァイオリン協奏曲集「四季」は、日本でもよく知られた名曲である。
ところが意外なことに、この作品が世界中で愛聴されるようになったのは、二十世紀の後半になってからだ。ところが意外なことに、この作品が世界中で愛聴されるようになったのは、二十世紀の後半になってからだ。ヴィヴァルディは生前ヴェネツィアで活躍し、高く評価されていたが、死後は同じような曲を何百と書いた才能のない作曲家と酷評され、ほとんど無視されるようになっていたのである。彼がウィーンで客死したことが判明したのもそう昔のことではない。
「四季」は、ヴァイオリンを独奏に立てた協奏曲である。ちょうど同じ時代、ヴェネツィアからそれほど遠くないクレモナという町でヴァイオリンを作っていたのが、アントニオ・ストラディヴァリだ。現在では数億円以上という法外な価格で取引される、いわゆる「名器」の製作者である。「四季」の華麗な独奏部分には、まだ新しい楽器だったヴァイオリンに対する新鮮な驚きが込められているはずである。こんな音色も、あんな音色も出せる。喜びから絶望まで表現できる。清らかな天使から邪悪な悪魔まで示せる。そういう多彩さを持つ楽器は、そうあるものではない。
「四季」には、季節折々の自然や人間の様子を表す、ソネットと呼ばれる短い詩が添えられている。ヴィヴァルディが書いた音は言葉を忠実に描写している。だが、演奏家は必ずしもそれに従うわけではない。ある女流は、まるで失恋した女の悲しみのような表情で弾く。ある若者は、青い感傷を込めて弾く。病んだ人間のひとりごとのように弾く人もいる。イマジネーションは無限である。古今の名ヴァイオリニストたちが、ユニークな解釈を競ってきた。フランス人は軽快で優雅に、ドイツ人は無骨だが律儀に、と演奏家のお国柄もよく出る。
楽譜はひとつである。その楽譜がいつどこでどのような意図で書かれたか、またどのように演奏されていたかを研究するのは学問の領域だ。しかし、いくら研究が進んだとて、演奏家にとって一番大事なのは自分の音楽。芸術とは、正解探しではない。誰も知らなかった美の創造であり、自己表現だ。ひとつの曲が演奏されるとき、そこではしばしば知性と感覚、学問と芸術の衝突が起きる。
「四季」を、あれこれCDで聴き比べてみるのは楽しい。今度はどんな演奏が行われたのだろう。わくわくしながら私はCDの封を切る。
『三色旗』2015年4月号掲載
※職位は公開当時のものです。