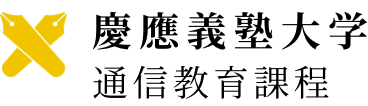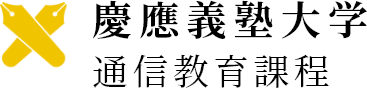教員メッセージ
テキスト科目

2018年にテキストを全面的に改訂しました。長年にわたって慶應義塾大学には法哲学の専任教員がいなかったこともあり、内容が相当に古びてしまっていたからです。もちろん法哲学は2500年にわたる西欧近代法の歴史とともに歩んできた悠久の存在ではありますが、それでも1970年代以降は正義論、つまり正義にかなった社会のあり方や制度の基準はどのようなものかを考える分野を中心として、グローバルな展開が進んでいます。今回の改訂では、そのような状況を踏まえて英米圏の哲学に立脚した正義論を主な対象にしました。もとよりそれは、テキストの紙幅や学習時間とのバランスから導かれた一定の限界内で構成された、ある特定の法哲学であるにすぎません。上記のように内容の焦点を設定したことにより、たとえば法解釈方法論や権利・義務といったものの性質を分析する分野である法概念論、あるいはドイツ圏の哲学に由来するさまざまな理論は射程から外れることになっています。それらに関心のある学生には、テキストやそこで提示される参考文献を足がかりにして、他の教科書や研究書へと学習を進めていってほしいと考えています。哲学は本来、既存の観念を疑い自ら考える学問です。問題へと主体的に取り組む姿勢を、法哲学のテキストと学習から身に付けてほしいと願っています。

- 著書
-
- 『法解釈の言語哲学』(勁草書房、2006年)
- 『自由とは何か』(筑摩書房、2007年)
- 『自由か、さもなくば幸福か?』(筑摩書房、2014年)
- 『法哲学』(共著、有斐閣、2014年)
- 『法哲学と法哲学の対話』(共著、有斐閣、2017年)
スクーリング科目
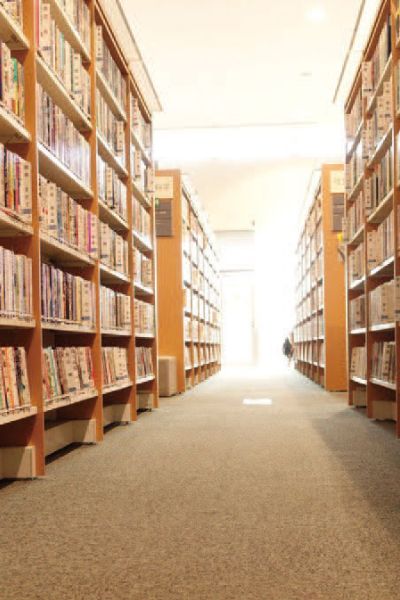
しばらく前から、「分断」がアメリカを語る際のキーワードになっています。人種や宗教など個人のアイデンティティに基づく対立が深まっただけでなく、それが党派対立とも対応するようになり、2021年1月には選挙の結果を受け入れない暴徒が連邦議会議事堂を占拠する事件まで起きました。今や、民主主義の「後退」まで危ぶまれています。
これは憂慮すべきことですが、どれ位新しく、深刻なことなのでしょうか。例えば南部で19世紀半ばまで奴隷制が、また1960年代まで投票権の差別を含む法的な人種隔離が残ったというように、人種をめぐる分断はずっと続いてきました。またひとくちに分断といっても、政治的な表れ方は様々です。連邦政府では必要な立法の成立も覚束ない一方、各州の政府では人工妊娠中絶規制など、イデオロギー的な特色のはっきりした政策が次々に実現しています。この授業では、目の前の出来事を理解するための座標軸を提供することを意識しつつ、現代政治の構造と歴史の両面からアメリカ政治のからくりを解説します。

- 著書
-
- Judicializing the Administrative State: The Rise of the Independent Regulatory Commissions in the United States,1883-1937 (Routledge, 2019)
- 『アメリカの政党政治―建国から250年の軌跡』(中央公論新社、2020年)
私の専門分野は、刑法学です。刑法とは、犯罪と刑罰に関する法律のことをいいます。主として、どのような条件がそろったときに犯罪の成立が認められるかについての理論的研究をするのが、刑法学の役割です。社会の安全を守るためには刑罰を用いて犯罪を防圧する必要があります。他方で、国家による刑罰の濫用を防ぎ、市民の自由を守る必要もあります。この両者のバランスをどうはかるのかが、刑法学の課題です。
私は、元々、犯罪を行おうとしたが失敗した場合(犯罪の未遂)について、なぜ処罰することができるのかという問題に関する理論研究を行ってきました。最近では、この研究によって得た知見を活かし、特殊詐欺をめぐる刑法上の諸問題の研究に取り組んでいます。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺や還付金詐欺など最近社会問題化している詐欺の形態の総称です。特殊詐欺は失敗に終わることも多いため、どの範囲まで処罰可能かが捜査の現場や刑事裁判で大きな問題になっているのです。
このほか、他大学の研究者と連携しつつ、犯罪者が犯罪から得た利益を剥奪するための制度に関する調査研究も進めています。

- 経歴
-
2000年 慶應義塾大学法学部卒
2006年~2010年 同学部専任講師
2010年~2016年 同学部准教授
2016年 現職。博士学位取得。 - 著書
-
- 『未遂犯と実行の着手』(慶應義塾大学出版会、2016年)
- 「<ケーススタディで考える特殊詐欺> 未遂・承継的共同正犯」法学セミナー779号(2019年)10頁以下
- 「実行の着手、早すぎた構成要件実現」法学教室471号(2019年)91頁以下