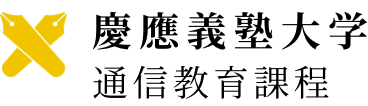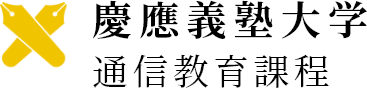秋の七草

文学部教授
藤原 茂樹
「ちかまさり」という古いことばがある。離れて眺めているよりも、近づけば近づくほど美しくみえる女性のよさをいう。こまやかなものに美をみつめる日本人のまなざしは、想像以上に古い時代からのもののようだ。七〜十月にかけて咲くカワラナデシコ(大和撫子)は、差し詰め近優りする花の代表格として万葉の時代から愛おしがられていた。一株から七—九本の茎がわかれ、それが日を追って開いていく。淡紅色の小さな花が咲いた初日に、顔を近づけると、ほんのりとよい香りがし、翌日にはもう香りが薄れている。五弁の花びらの縁はそれぞれ二十ほど細い糸状に裂けていて、目を近づけてみると愛らしいことこの上ない。山上憶良が歌った秋の七種の一つである。
万葉の時代は、野で遊ぶことを楽しみにしはじめた時代だった。秋も盛りの頃の歌。
秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば七種の花 *五七五七七
萩の花尾花葛花なでしこが花をみなへしまた藤袴朝顔が花 *五七七五七七
秋の野に出た憶良が、こどもたちに向かって、花の名を教えているという説がある。指を折って数えてみるとね、野には七種(「くさ」は、種類の意味)の花があるよ、と歌いだして、つぎに、七つの花の名を込めて歌う。花の名を七つ揃えるには二十五文字ほどかかる。『万葉集』では、〜の花〜花とすることが多いので、「花」をつけたりつけなかったり加減して十一文字程度を加えると、三十一文字から、こぼれだしてしまう。そこで、すこしばかりひねって、みそはちもんじ、つまり旋頭歌(五七七五七七)に仕立ててしゃらっとしている。形式のちがうでこぼこの組み合わせなど気にもせず目を輝かせているあどけない顔が思い浮かぶ。花の名以外に加えたのは「また」という二文字だけだった。これが絶妙なアクセントになっている。
秋の野には他に、竜胆・刈萱(枕草子)、紫苑(古今集)、忘れ草(ヤブカンゾウ 万葉集)なども、咲いていたのではないだろうか。七は、日本人が古来好む数のひとつだ。平安になると、憶良の七種を追っかけるように、春の七草が編み出される。これは食用の七草で、察するところ宇多天皇の時代に宮中から言い出されて広まっていく。
そういえば、向島百花園の花壇に「夏の七草」の説明があった。
菊桔梗 蓮女郎花 しますすき 小車 仙翁
「星祭りの花扇の七草」とある。字足らずでも好ましい。室町の頃の七夕の朝、公家から宮中に、花で造った一抱えもある大きな花扇が届けられた。秋のはじまりの七夕にかけて七の草が、語呂合わせにほどよい。夏とはいうが、七夕は以前はもう秋。憶良に対抗したもうひとつの秋の七草の歌といえる。
でも、憶良がなぜ七種にしたかはわからない。わからないままに、私たちは好ましく思い続けている。
『三色旗』2015年10月号掲載