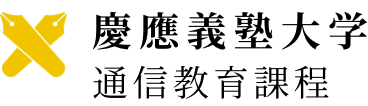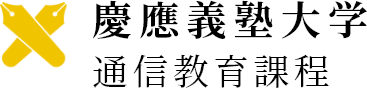教員紹介 岩間一弘

文学部教授
岩間 一弘
東洋史学は多くの地域・人々・テーマとかかわる広範な学問分野といえますが、そのなかでも私は二〇世紀上海をはじめとする中国都市史、および近現代東アジアの食文化を中心とする国際交流史を研究しています。ここではまず私自身の学問遍歴に沿って、東洋史学の研究視角をご紹介したいと思います。
一九九一年に上海を初訪問してから四半世紀が経過し、高度経済成長とそれに伴う急激な社会変化を実体験することになりました。私が中国に通い始めた頃から漠然と不思議に感じていたのは、東京などとは異なって当時の中国社会では、サラリーマン(ないしはホワイトカラー)を中心とするミドルクラスが目立たないことでした。私は中華民国期・人民共和国初期の雑誌・新聞記事、都市行政・企業経営文書などを読み漁った末、東京などと同じように上海でも都市中間層が一度は勃興し、近代的な大衆消費文化を花開かせてそれを謳歌してはいたものの、日中戦争期以降の経済的困窮や共産党政権樹立後に連鎖的に発動された大衆運動の圧力のなかでしだいに消失(ないしは潜伏)し、一九九〇年代に至っていたことをつきとめました。
こうして二〇世紀上海の社会・文化変容の軌跡が、東京のものとはかなり違うようだとわかってくると、今度は東アジア史というより広い視野から、こうした相違が生まれた背景を知りたいと思うようになりました。それに伴って、上海や東京と同じように二〇世紀に発展した香港・台北・天津・ハルビン・ソウルなどの国際都市の形成史にも興味をもちました。さらにもともと食いしん坊でエンゲル係数が高かったところに、商科大学の教員の身分で上海に留学していた当時に飲食店チェーンの経営に奮闘する友人と身近に付き合えたことなどから、これまた東洋史学としてはやや特殊な食文化の国際交流という研究テーマに取り組むことになりました。
交流史は、一地域・一国の歴史をよりマクロな視点から捉え直す可能性を開きます。私がそれを特に面白く感じるのは、中国・日本・韓国などの東アジア各都市で起こった歴史的な出来事の間に、思わぬ連鎖関係を見いだせたときです。例えば、台湾・朝鮮を植民地とした日本では、植民地の食料が流入して農産物の価格が下がり、それによって困窮化した農民が第一次世界大戦期の好景気で都市に流入して米の需要が高まっているところに、軍部がシベリア出兵用の軍用米を大量に買い付けると、米の売り惜しみが起こって暴動にまで発展します。野沢豊氏の研究によれば、こうした米騒動を機に成立した原敬内閣が中国から米穀購入を行うと、中国にも米不足・米価高騰が波及して、各都市の学生・労働者が日本への米糧輸出反対運動を起こし、一九一九年の五・四運動(ヴェルサイユ条約への調印拒否に至る反日本帝国主義運動)の展開に大きな影響を与えました。日本・中国・朝鮮・台湾の食糧供給が密接に相互連関していたばかりでなく、日本の米騒動と中国の五・四運動が連動していたことがわかるでしょう。
食文化の越境は、現在では多国籍企業のマーケティングによることが多いのですが、二〇世紀の歴史を振り返ると、戦争・軍食、食物外交(food diplomacy)、帝国と植民地の拡大、革命、亡命、移民、観光・街作りなど、多様な要因によって進んできたことがわかります。現在ではこうした交流史の観点からする研究も、着実に独創的な成果を蓄積しつつあります。例えば、近代朝鮮の西洋料理は、二〇世紀最初の数年間はロシア、それ以後は日本のフィルターを通して受容されたこと。台湾ではカレーライスがインド→イギリス→日本を経由して植民地期に受容されていたこと。ロースハムやバームクーヘンなどは第一次世界大戦期に日本が攻撃したドイツの租借地・青島からやってきたドイツ人捕虜によって日本にもたらされたこと。一九二七年に新宿中村屋喫茶部の看板メニューとして出された「印度式カリー・ライス」には、日本に亡命したインドの独立運動家R・B・ボースの反植民地闘争の思いが込められていたこと。中国における日本の軍国主義的な拡張が、日本における中国料理の普及に重要な役割を果たしたこと。ラーメン博物館などで語られる日本のラーメンの歴史物語は、引揚げ者(日本人)の役割を強調して朝鮮人・中国人労働者については多くを語らない「ラーメン・ナショナリズム」があることなどが論証されています。
ここでは近現代東アジアの都市史・食文化史に関するテーマをご紹介しましたが、最後に強調したいのは、歴史学の研究課題は無限にあり、人、物、カネ、社会現象、文化・芸術など、何を題材に取り組んでもよいということです。自らの人生に深く関わった出来事や、日常的に接する身近な物事などから、激動する東アジア史のドラマを探り当て調べ上げていくことは、とても充実した楽しい勉強になるでしょう。同時に、必要な文献資料を収集し、関係者へのインタビューを積み重ね、それらを丹念に照合し、もし思い通りの結果が得られなければ構想を練り直すという試行錯誤は、かなりの労苦を伴うかもしれません。歴史研究を成功に導く鍵は、一縷のひらめきと多くの地道な作業にあるといえます。ユニークな問題意識をもって東洋史研究の苦楽を分かち合える方々にお会いできるのを楽しみにお待ちしております。
『三色旗』2016年4月号掲載
※職位は公開当時のものです。