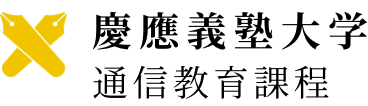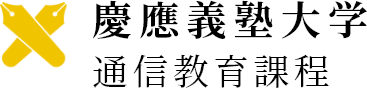人文・社会科学は役に立つか

文学部助教
上野 大輔
今に始まったことではないが、「その学問が何の役に立つのか」という問いを耳にすることがある。皆さんも、家族や知人から尋ねられた経験があるのではないか。また、自らこの問いを発したという方も、いらっしゃるかもしれない。いわゆる実学(実用的と思われている学問)ではない学問分野に対して向けられることの多い問いであるが、昨今では人文・社会科学が主なターゲットになっていよう。
どの学問分野に取り組む者であっても、「何の役に立つのか」という問いにそのまま答えることはできるはずである。しかし、それで十分なのだろうか。財界のみならず、政府までがそうした問いを発し、それに迎合するような動きが大学にも散見する状況下にあっては、そうした問い自体を問い返す必要があるのではないか。
もっとも、経済が悪化しているので各学問分野への対応を見直さざるを得ないという主張もまた、切実なものであるに違いない。こうした主張に直面する時、日本史を専攻する筆者は、先のアジア・太平洋戦争を想起する。当時の日本では戦局の悪化を受け、文科系の学生も動員された。「役に立つ」理科系の学生は多くの場合、兵士としての動員は見送られた。そして夥しい死傷者を出し、敗戦を迎えたのである。今日の日本では、経済の悪化を一方で受け、人文・社会科学系の学部・大学院の「見直し」が進められている。無論それだけで、巨大な財政赤字をはじめとする経済問題が解消することはない。
敗戦前の日本では、近代的な人文・社会科学を導入したものの、国民的な定着を見ず、土壇場で神がかり的な扇動に流された。エルウィン・ベルツの心配も手がかりとなるように(トク・ベルツ編・菅沼竜太郎訳『ベルツの日記(上)』岩波文庫、一九七九年、二三七~二四一頁)、すぐに役立つ部分を中心に「文明」が取り入れられ、その基盤となる人間像・社会像が思想として、しっかりと学ばれなかったのである。
その反省から出発したはずの敗戦後も、経済的な豊かさの追求へと流され、近代社会の基盤となる人間像・社会像と国民的規模で向き合うことが乏しかったのではないか。それが、経済のみならず人権・憲法・原発・外交などをめぐる数々の困難と繫がっているように思われてならない。困難だから人文・社会科学はいらない、というのではなく、人文・社会科学的な知が軽視されたことこそが、困難の元凶になっているのではないか。ここに至り、表題の問いかけは、問い直されることとなる。
『三色旗』2016年6月号掲載
※職位は公開当時のものです。