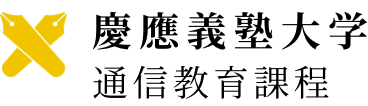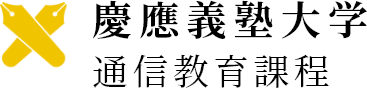太宰治の『心の王者』

文学部教授
斎藤 太郎
近代的私学の草分けだけに慶應義塾には本邦初の事柄が多いが、大正六年創刊の学生新聞「三田新聞」もその例に漏れない。大正期、昭和戦前期・戦後期の慶應義塾大学の状況や学生生活を知る上で興味のつきない極めて貴重な資料である。
その「三田新聞」昭和十五年一月二十五日号に、太宰治が『心の王者』という短文を寄せている。第二次大戦勃発から四ヶ月が経過し、一年十ヶ月後には太平洋戦争の開戦を控えて、日本が急速に戦時体制を整えつつあった時期に発表されたこのエッセイを、太宰は原稿依頼に訪れた「三田の小さな学生さん二人」の描写から始めている。少年のおもかげを残しながらもいっぱしの編集者さながら世慣れた振る舞いを見せる彼らに接するうちに、彼には「今の学生諸君の身の上」が「不憫に思われてくる」。それは、本来「社会のどの部分にも属してい」ない、「また、属してはならない」はずの学生が、「誰かに、そう仕向けられ」て「老成の社会人になりきる﹂という」おそろしい堕落﹂を強いられているからだというのである。
学生は「思索の散歩者」でなければならない、と信じる太宰が、それでは学生本来の姿とはなにか、という問いに対し、「答案」として提出するのがドイツの詩人シラー(一七五九― 一八〇五)の物語詩『地球の分配』である。彼が紹介するこの詩の概略はこうだ―「受けとれよ、この世界を![・・・・・・]さあ、仲良く分け合うのだ」というゼウスの呼びかけに、様々な身分、職業の人間たちが、取り分を求めて先を争う。ところが、世界の分配がすっかり終わり、地上のものすべての所有者が決したころになって、詩人が「のっそり」やってくる。なんら分け前に与ることができなかったことを嘆く詩人は、「お前は一体何処にいたのだ」と問うゼウスに、自分の心は地上のことを忘れて天上界にあったのだ、と答える。これに対してゼウスは、詩人が手にできる地上的な財はもはやないが、そのかわりに、いつでも好きな時に神々の天上界に遊ぶことができるという特権を認めてやる―
学生だけに許された特権とは、この詩人と同じく、「地上の営みに於ては、何の誇るところが無くっても、其の自由な高貴の憧によって時々は神と共にさえ住める」ところなのだ、というのが太宰の主張である。学生が﹁地上の分割﹂に与ることに早くも汲々としているように見える当時の状況をにらみながら、彼は慶應の学生に向かって「陸の王者」を歌うばかりでなく、「心の王者」を以て自任せよ、と訴えかける。安保法制や憲法改正をめぐって、なにやらきな臭い世情の中で、大学に「即戦力」育成を求める政財界の圧力が強まっているいま、叫びにも似た太宰の訴えは思いがけぬアクチュアリティを帯びているように思える。社会人として活躍しつつ学んでおられる方が多い通信教育課程の皆さんは、太宰治の学生論をどう読まれるだろうか。
『三色旗』2016年8月号掲載
※職位は公開当時のものです。