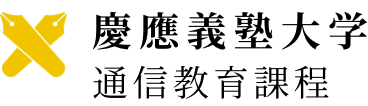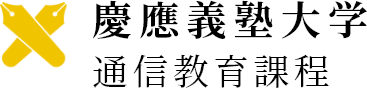No Art, No Life?

法学部教授
横山 千晶
趣味は何ですか、と聞かれると、読書、映画鑑賞、音楽、美術館めぐり、と答える人たちも多いだろう。都心にいればさまざまな美術館に足を運ぶことができるし、ソーシャルメディアのおかげで「芸術」はもっと身近な存在になっている。いや、ソーシャルメディアの中で語ることそのものがすでに創造的な活動なのだろう。
しかし、「芸術」 とはなんだろうか。「術」と付くからにはそれは何らかのスキルなのだろうか。確かにartという言葉はもともと「技術」を表す言葉で、レイモンド・ウィリアムズの『キーワード辞典』によれば、英語としては十七世紀末まで実にさまざまな技術一般に使われていたという。その意味でartistとartisanとは同義であったといえる。しかし、十九世紀になると想像力を駆使した創造性に富む活動を行うartistと熟練労働者をさすartisanは分けられていくようになる。もっといえば手に職を持たない労働者たちはoperativesとして機械工場の生産体制の土台となっていく。
二十一世紀の私たちはロボット工学の台頭によってあらためて労働の意味を考えるようになったが、産業革命以後のイギリスでも同じように労働の意味、生きていくことの意味を模索するようになったことはいうまでもない。蒸気機関という動力を得て二十四時間人々を働かせることが可能になった「世界の工場」で、労働力は国富と政治経済の土台となった。同時に一人の存在が労働力に変換されるとき、その人の持つ創造力は抹殺されることになる。文学者であり工芸家であったウィリアム・モリスは労働の真の意味を作り手と使い手の喜びであるべきとすると同時に、「芸術の目的は、休暇を楽しむことができるように、そして休んでいる間にも疲弊することがないように、美しく興味深い企画に参加してもらうことで、そして仕事においても希望と肉体的な楽しみを味わってもらうことで、人々の喜びを増すことです。つまり簡単に言えば、仕事は楽しく、休暇は充実したものとすることなのです。したがって、真の芸術は、人類にとっての純然たる祝福です」と述べ、生活の中での芸術の意味を日々の労働と補完しあうものとするのみならず、その行為への参加を促した。それは単に美術館をより多くの人々に開放する、などというトップダウンの短絡的な考えではなく、人々が日々の暮らしの中に創造的な行為を見出す、ということなのである。働くことだけではない。食べること、住むこと、憩うこと、他者とつながることといった一つひとつの営みをどれだけ充実したものとしていくのか、ということでもある。そこに必要なのは金銭ではなく、想像力であり、その想像力を発揮できる環境である。つまり、芸術とは誰にでも開かれた「術」であり、他者とつながる「術」なのだ。
二十一世紀に入ってすでに十五年以上たった今でも、モリスの説いたこのartの意義は有効だろう。それは日々の暮らしを少しでも充実したものとすること、しかも他者とともにそれを分かち合っていくことに他ならない。そしてそのような喜びを享受できる社会に住む私たちが、どれほど恵まれているのか、ということを思い起こさせることに他ならない。
『三色旗』2016年10月号掲載
※職位は公開当時のものです。